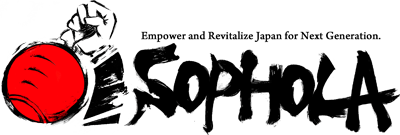Empower and Revitalize Japan for Next Generation
SOPHOLAのVision(目指す世界観)、Mission(果たす役割)、Values(大切にする価値観)を体現する取り組み・アイデアを発信。
SOPHOLAの雰囲気がわかるような社員の日常や想いも更新していきます。
Beyond the Summit:登山が導いた思考の拡張
はじめに — 登山は“問いを生きる場”
人生には、答えを出すためではなく、 問いを生きるためのフィールドがある。 私にとって、それが登山でした。
登山は「自己探求の加速装置」であり、 思考・感情・行動を同時に試される“人間の実験場”。 頂に立つたびに見えてくるのは、景色ではなく—— 自分という存在の、まだ知らない地図でした。
登山との出会い — 一言の衝撃から始まった
登山を始めたのは2023年5月。 きっかけは、息子のこども園での長峰山登山でした。
当時3歳の息子と一緒に登ったその日、 私は息を切らしながら、なんとか頂上に到達。 下山は車で降りたのに、翌日はふくらはぎが痛くて歩くのもつらかった。
翌朝、こども園でその話をしたとき、 一緒に登った一回り以上年上の保育士さんが笑顔で言いました。
「まさきさん、何言ってるんですか。全然疲れてませんよ。慣れれば大丈夫です。私、数年前に常念岳にも登りましたから。」
——その一言に、軽い衝撃を受けました。 私よりも年上の方が、あの常念岳に。
「いつか自分も登れるようになりたい」
それが、私の登山の出発点でした。
日常を再生するリハビリとしての登山
当時、起業と家庭を両立する中で積み重なったストレスを抱えていました。
登山は、体力づくりを目的に始めたはずが、次第に心を整えるための時間へと変わっていきました。
息子と登った霧訪山では、7合目で彼が 「パパ、もう疲れた。お家でビー(テレビ)見たい…」 とリタイア。
 My Son at Mt. Kirito
My Son at Mt. Kiritoその後も私は、一人で里山に登り続けました。
最初は息を切らしながら登っていた長峰山も、数ヶ月後には軽快に登れるようになりました。
「今日は計画通りに登れた」 ——そんな小さな達成の積み重ねが、 親として、伴侶として、経営者として 自信を失いかけていた自分を静かに立て直してくれたのです。
登山は“非日常への逃避”ではなく、 “日常を再生するためのリハビリ”でした。
そして家族登山には、また別の喜びがありました。 きつい坂を登りきって頂上で「よく頑張ったね」と笑い合う瞬間、 そこには下界では得られない一体感と幸福がありました。
戦略的登山 — 考えて登るということ
長峰山のあと、私は考え始めました。 「常念岳に登るには、何が必要か?」
長距離、標高差、岩場への慣れ。 そのすべてを段階的に身につけるため、 蝶ヶ岳、爺ヶ岳、南八ヶ岳縦走などに挑戦しました。
やがて常念岳に登頂した後、 かつて奥穂高岳から見上げた ジャンダルム、裏銀座、剱岳の稜線を「自分の足で繋ぐ」ことが 次の目標になりました。
そのために、 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根の日帰りピストンで体力を極限まで鍛え、 戸隠西岳〜本院岳のような難ルートで集中力と判断力を磨き、 鶏冠山では鎖場への対応力を高めていきました。

登山は、単なるピークハントではなく、 「自分の成長戦略を立て、検証し、修正する」行動学。 思考と行動のPDCAを最も短時間で回せるのが山なんです。
ハプニングを“素材”に変えるという思考
登山では、予期せぬ出来事が必ず起こります。 でも、嘆くか活かすかで、すべては“素材”に変わる。
奥穂高岳に挑んだ朝、 駐車場で登山靴を忘れたことに気づいた瞬間、頭が真っ白になりました。 何週間も準備してきた計画が、たった一つのミスで崩れる——。
けれど数分後には、こう考えていました。 「ジム用のシューズがある。滑るかもしれない。でも慎重に登ればいい。」

ルートを修正し、奥穂高岳と涸沢岳の2峰に集中。 翌朝、涸沢岳の山頂で迎えたご来光の中で、 連なる奥穂・前穂・ジャンダルム・槍の稜線を見た瞬間、 胸の奥から強く思いました。
「ああ、この世界は、もうすでに繋がっているんだ。」
AIという“意識の外部化装置”
気づけば登った山の数は100座を超えていました。 登山ごとに「経験 → 記録 → 新しい理解 → 次の設計」というサイクルを回してきましたが、 2025年からはそこに新しい要素が加わりました。
それが、AI(ChatGPT)です。
AIに自分の山行記録を読み込ませると、 「どの区間でペースが落ちたか」 「どんな判断が功を奏したのか」 を客観的に分析してくれる。
自分の感覚とAIの視点を照らし合わせながら、 次の山行を設計するようになりました。
AIは単なるツールではなく、 自分の意識を外部化し、思考を可視化する“もう一人の自分”。
登山が思考の内省を促すように、 AIはその内省を加速させてくれる“思考の相棒”です。
登山が教えてくれたこと
私にとって、 「生きるとは、自分の可能性を探究しきること」。 それは十代の頃、ユングの“個性化(Individuation)”の思想に出会って以来、変わらない人生観です。
「人が自分を理解しきるには、人生はあまりに短い」—— その言葉に救われ、 私は限られた時間の中で自分という存在を どこまで深く掘り下げ、広げられるかをテーマにしてきました。
そして登山に出会い、 その「探究の方法」としての圧倒的な有効性に気づいたのです。
登山は、思考と行動が一体化した“探究の現場”。 計画を立て、判断し、行動し、結果を受け止め、次に活かす。
そのすべてが、自分という存在の理解を一歩ずつ深めてくれる。
しかも、そのサイクルはビジネスよりも圧倒的に速い。 山では数時間でPDCAを回せる。
だからこそ、登山は自己理解の速度を飛躍的に高めてくれる。
おわりに — 自己探求という終わりなき登山
自然は、いつも静かに問いかけてきます。 「あなたは、どう生きたいのか?」と。
だからこそ、登山は私にとって “自分を知るための最良の方法”であり、 “人生を実験的に探究する場”になりました。
山もAIも、そして日常も—— すべては、自分を映す鏡です。
私はこれからも、 考えながら登り、登りながら考える。 そんな生き方で、 人生という長い山を登り続けていきたいと思います。